最近は洋風の家が好まれますが、やっぱり畳のある和室って清々しいですよね。
昔ながらの畳作りに機械の良さを最大限に取り入れる。良いものを残しながらも現代の需要に応える。その全てには、熟練の職人の経験と知識と知恵と腕がありました。

木更津市の林畳店、社長の林 保一さん。お祖父様の代からから3代目なのだそうです。

近頃は黒、濃い茶色、ピンクなどの色付きの変わった畳も需要が多いそう。い草と藁で作る畳は凹凸ができてしまうそうですが、和紙をこよりにして作る科学床の畳は真っ平らに仕上がるのだそうです。手で作る畳もありますが、いまはほとんどが機械での作業。
時代は変わりましたね。

機械で作る科学床の畳がオススメなの? それとも逆に手で作る昔ながらの畳の方が「良いもの」なの? と悩みそうですが、「手で作る方が良いものが作れると思いがち。でも機械は製品が安定するんです」と、林さんは説明します。
力加減を締めようと思えばいくらでも締められる。畳を張ろうと思えばいくらでも張れる。でも機械だと真四角なものしかできないのも事実。

「『手』じゃなければできない作業もあるんです。柱に合わせたりした変わった形のものはすべて手作業でしかできません。ならば機械の作業はだれでもできるのか、といえばそうじゃない。『なぜここを押さえるのか』『なぜここを引っ張るのか』という理屈が分かっていないとできないんです。」
分かりやすく、熱意を持って説明してくださいました。

畳の需要が少なくなってとても残念に思っている方は少なくないはず。こうした地元の技術が継承されるように、畳を使ったおしゃれな家づくりも増えていくといいですね。
(イメージモデル:秋谷佳奈)



























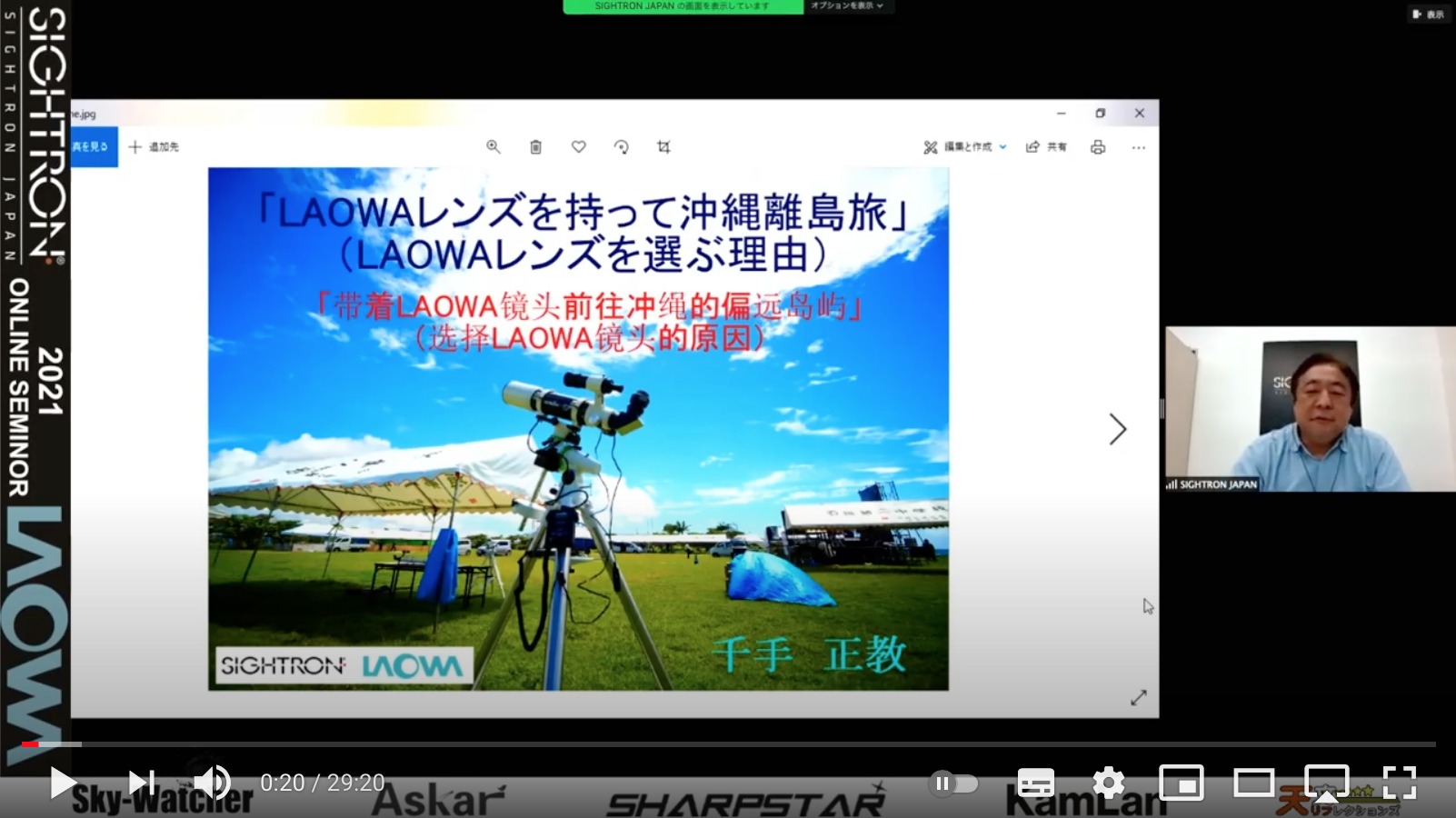 内房出身プロカメラマンによるオンライン講座
内房出身プロカメラマンによるオンライン講座